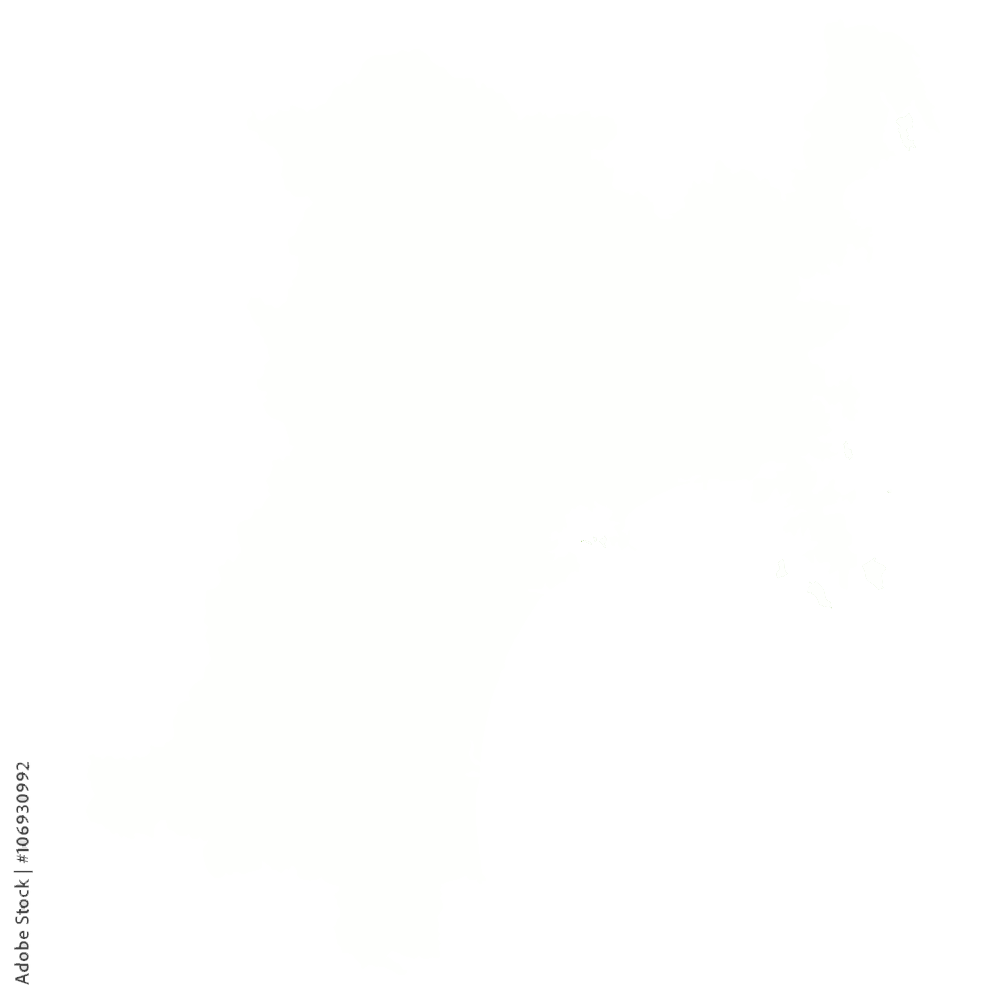【2025/1/5執筆】
「電気工事」はイメージとしては持ちやすいと思いますが、許可取得という法的場面では思いのほか細心の注意を払う必要があります。
どのような工事が「電気工事」に該当するか、また許可取得の場面でどういった点に注意が必要か見ていきましょう。

「電気工事」の内容
建設業許可上の「電気工事」は、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事を言います。
具体的には、以下のような工事が電気工事に該当します。
- 発電設備工事
- 送配電設備工事
- 引込線工事
- 変電設備工事
- 構内電気設備工事(非常用電気設備を含む)
- 照明設備工事
- 電車線工事
- 信号設備工事
- ネオン装置工事 等
いかがでしょうか。一般的な電気工事ですのでイメージしやすいのではないでしょうか。
「電気工事」の考え方
屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当します。
太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事も含まれます。
「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類のの設置に関する工事が含まれますので、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防設備工事」等と重複する場合もあります。この場合は原則として「電気工事」等それぞれの専門工事の方に区分するものとし、これらのいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置は「機械器具設置工事」に該当するものとされます。
「電気工事」の許可を取得するための専任技術者の主な資格
電気工事の許可を取得するために専任技術者に必要な主な資格は以下のとおりです。
| 1級電気工事施工管理技士 |
| 2級電気工事施工管理技士 |
| 第1種電気工事士 |
| 第2種電気工事士(資格取得後3年の実務経験が必要) |
上記の資格を保持していなくても「電気工事」に関する実務経験があり、これを証明できれば専任技術者になることが可能です。
必要な実務経験はまずはその方の学歴によって異なってきます。
「電気工学」「電気通信工学」に関する学科を卒業している場合には、高校卒業なら5年以上、大学卒業なら3年以上の内装仕上工事に関する実務経験があれば、専任技術者となることができます。
高度専門士や専門士の称号を持っている場合は大学卒業と同様に扱われます。
これら指定学科を卒業していない場合には「電気工事工事」に関する10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。
これら実務経験は過去の注文書等の確認書類が必要であり、書類上実務経験が確認できて初めて専任技術者として認められます。
ただし、電気工事に関する実務経験に関しては、他の許可業種と異なり注意が必要です。
証明する実務経験については、電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第3条の規定による登録(いわゆる「電気工事業登録」)を受けて営業した期間において従事したもののみが実務経験として認められます。
例えば「第2種電気工事士」の場合は資格取得後3年間の実務経験が必要ですが、この3年は所属した会社(事業主)が「電気工事業登録」を受けていることが前提で、電気工事業登録を受けていない会社(事業主)での経験は実務経験として原則認められないということです。
(著者)行政書士 方波見泰造(ハイフィールド行政書士法人)

行政書士歴10年。建設業許可に関しては新規・更新・各種変更手続きの他、経営事項審査申請のサポートと入札参加資格申請を東北六県、関東で対応中。顧問契約で許認可管理も行っている。行政書士会や建設業者でも建設業許可に関する講演・セミナー実績あり。
【保有資格】行政書士、宅地建物取引士(登録済)、経営革新等支援機関
経済産業省認定経営革新等支援機関として企業の資金繰をサポートするほか、不動産業(T&K不動産)にて事業用地の仲介も行う。
許認可という企業の生命線をしっかり管理しながら、資金繰りと事業用地という経営の土台も支える行政書士として日々研鑽を行う。