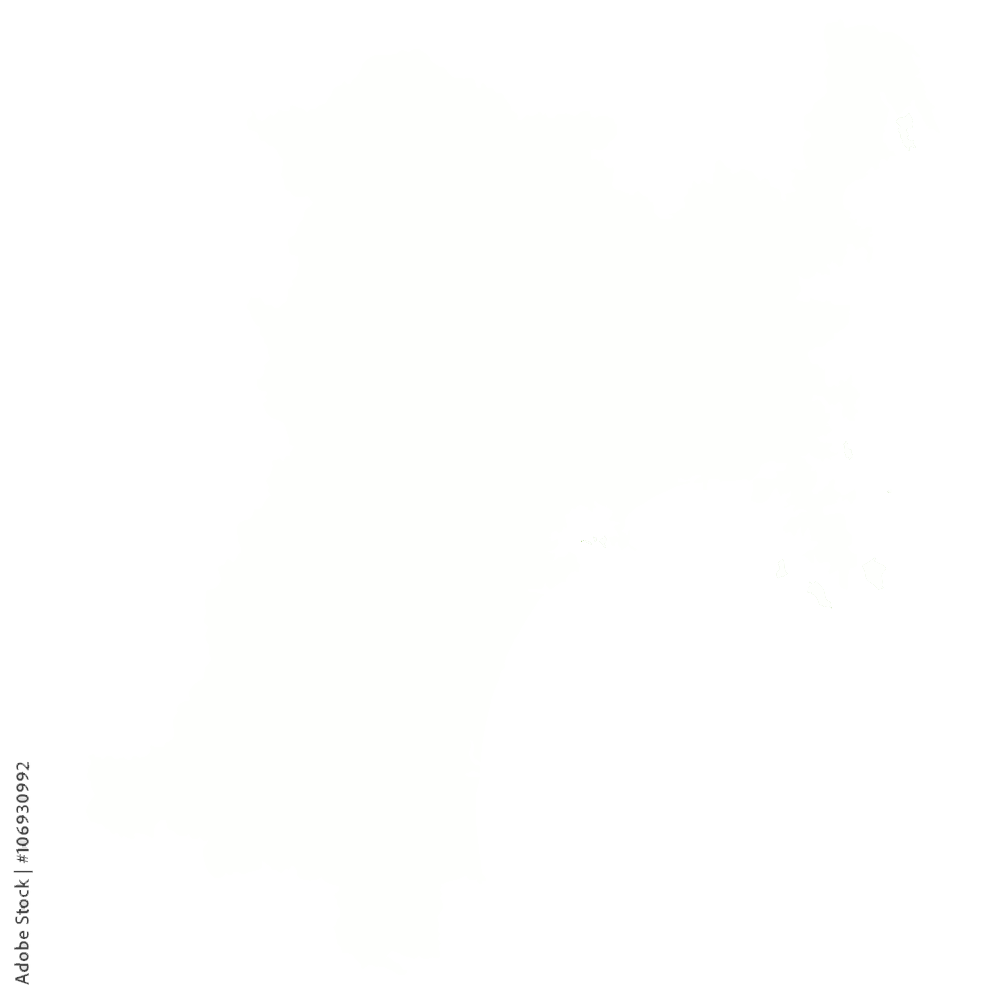解体工事業を営もうとする場合には、事業を行おうとする地域(工事を施工する区域)を管轄する都道府県知事の登録を受けえう必要があります。
これが「解体工事業登録」です。
この場合、既に「土木一式工事」「建築一式工事」「解体工事」のうちいずれかの建設業許可を有している場合は、登録の必要はありません。
ただ、ここに誤解を生む余地がありますので説明いたします。

解体工事業登録の考え方
まず、解体工事を営むのであれば少なくとも「解体業登録」が必要であり、既述の建設業許可を持っていればその登録が不要であるという話をしました。
このお話はご存じの方も多いと思います。
では続きを説明します。
建設業許可を持っていない場合、持っていても「土木一式」「建築一式」「解体」以外の許可である場合には解体工事業登録が必要となりますが、それは500万円未満の解体工事を行う場合の話です。
それでは500万円以上の解体工事を請け負う場合はどうするのか。
その場合には原則に立ち返り、建設業許可が必要となります。
つまり、500万円未満の解体工事を施工するなら解体業登録で可、500万円以上なら建設業許可が必要、という話に帰結するわけで、3業種いずれかの許可があれば登録の必要がないという話は表現を変えただけの話なのです。
3種目いずれかの許可を持っていればどんな解体工事でも請け負えるのか
では、「土木一式工事」「建築一式工事」「解体工事」のいずれかの許可があれば解体工事は何でも請け負えるのでしょうか。
応えは「NO」です。
解体工事には2つの考え方があります。
1つは、元請けとして総合的な企画、指導、調整のもとに「土木一式」「建築一式」工事として解体工事を行う場合
もう1つは、上記以外の場合、つまり専門工事として解体工事を行う場合です。
「土木一式工事」「建築一式工事」の許可をもって解体工事登録不要とされるのはあくまで「元請けとして総合的な企画、指導、調整のもとに「土木一式」「建築一式」工事として行う」解体工事の場合です。
そのため、下請けの専門工事として解体工事を行う場合は「土木一式」「建築一式」の許可を持っていても、「解体工事」の許可を持っていなければ解体工事業登録が必要なのです。
この点、理解しておく必要があります。
(著者)行政書士 方波見泰造(ハイフィールド行政書士法人)

行政書士歴10年。建設業許可に関しては新規・更新・各種変更手続きの他、経営事項審査申請のサポートと入札参加資格申請を東北六県、関東で対応中。顧問契約で許認可管理も行っている。行政書士会や建設業者でも建設業許可に関する講演・セミナー実績あり。
【保有資格】行政書士、宅地建物取引士(登録済)、経営革新等支援機関
経済産業省認定経営革新等支援機関として企業の資金繰をサポートするほか、不動産業(T&K不動産)にて事業用地の仲介も行う。
許認可という企業の生命線をしっかり管理しながら、資金繰りと事業用地という経営の土台も支える行政書士として日々研鑽を行う。