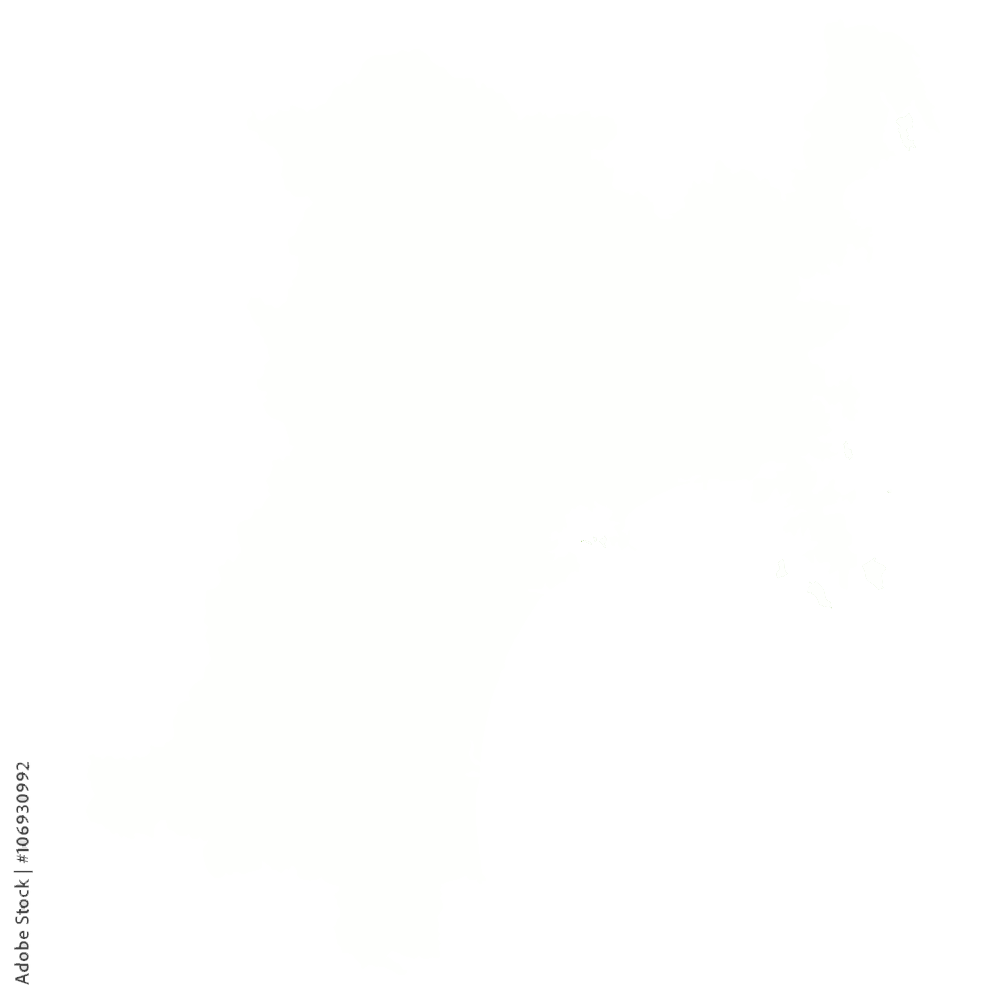【2025/1/4執筆】
令和3年と令和5年の法改正によって、若干の「営業所専任技術者」の要件緩和が行われました。
これから実務上の対応が増えてくることも見込まれますので、ご説明します。
一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和
この点「一般建設業許可」についてですのでご注意ください。
いわゆる「施工管理技士」に関して令和3年と令和5年に大きな制度変更がありました。
まず、令和3年4月1日施行の「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」によって、「技士補(技術検定1級・2級の第1次試験合格者)が申請されました。
その後、令和5年7月1日施行の「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」によって一般建設業許可の営業所専任技術者の要件が緩和されました。
具体的な緩和の内容は以下のとおりです。
1級の第1次検定合格者(技士舗)を大学指定学科(建設業法施行規則第1条に掲げる学科のことを指します。建築学や土木工学に関する学科等で、従来の専任技術者要件でもあります)卒業者と「同等」とみなし、また、2級の1次検定合格者(技士舗)を高校指定学科卒業者と同等とみなすこととされました。
これにより、従来の「大学の指定学科卒業後3年以上の実務経験」「高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験」と「1級の第1次検定(技士舗)合格後3年以上の実務経験」「2級の第1次検定合格(技士舗)後5年以上の実務経験」が、建設業許可取得における実務経験証明という点ではそれぞれ同等の要件となります。
ただし、例えば「1級、2級土木施工管理技士」「1級、2級建築施工管理技士」が専任技術者となることができる業種について「1級、2級土木施工管理技士」「1級、2級建築施工管理技士舗」がそれぞれ3年又は5年以上の実務経験を積めばすべての業種について専任技術者になれるのか(つまり実務経験を別にすれば、専任技術者となれる業種は「施工管理技士」=「技士舗」なのか)というと「イコールではない」というのが結論ですので、少々複雑です。
技士舗にて許可取得をご検討の際はまずご相談ください。
【関連知識】営業所専任技術者は出向者でも認められるのか
結論としては「可能」です。(自治体によって判断は異なります)
出向者を専任技術者とする場合は、通常の常勤性確認資料のほかに以下のような確認資料を求められます。この点は管轄自治体の判断は異なりますので、十分に事前確認を行いましょう。
ただし、原則として出向者を「工事現場の配置技術者」にすることはできませんので注意してください。
出向者の常勤性を確認するための追加資料(例)
- 出向契約書・覚書(契約書等の出向者の氏名が記載されていなければ誰の書類なのか分かりませんので、別途出向命令や辞令等で証明する必要があります。)
- 賃金相当分の負担先(出向元なのか出向先なのか)が確認できる書類
- 健康保険被保険者証
- 出向先の出勤簿
(著者)行政書士 方波見泰造(ハイフィールド行政書士法人)

行政書士歴10年。建設業許可に関しては新規・更新・各種変更手続きの他、経営事項審査申請のサポートと入札参加資格申請を東北六県、関東で対応中。顧問契約で許認可管理も行っている。行政書士会や建設業者でも建設業許可に関する講演・セミナー実績あり。
【保有資格】行政書士、宅地建物取引士(登録済)、経営革新等支援機関
経済産業省認定経営革新等支援機関として企業の資金繰をサポートするほか、不動産業(T&K不動産)にて事業用地の仲介も行う。
許認可という企業の生命線をしっかり管理しながら、資金繰りと事業用地という経営の土台も支える行政書士として日々研鑽を行う。